- インターンプロジェクト
- 移住
The Digital X 合同会社 代表取締役インタビュー
授業のない長期休み(夏・冬休み)や、在職中でも長期休暇がとれるタイミングを活用して、インターン先の企業から給与の支払いを受けながら、地域課題解決に取り組むことができるインターンシップ対応型プロジェクトである「青森暮らしインターンプロジェクト」。「青森暮らしインターンプロジェクト2024」に参加してくださった、The Digital X 合同会社代表の奈良岡和也さんに、インターン学生がインタビューを実施しました。
これからの青森県での暮らしに貢献する担い手を創出する皮切りとなる本企画。本企画を通じて青森県の経営者はどのように人生と事業を振り返るのでしょうか。青森で暮らすことを決めた経営者に対して、理想の社会への実現に向けた、事業への意気込みをインターン生が伺います。
過去の苦悩と成長のきっかけ
─自己紹介と事業の紹介をお願いします。
The Digital X合同会社代表社員の奈良岡和也と申します。もともと青森県弘前市出身で、高校を卒業した後に上京して、スノーボードメーカーに勤めました。その後、、IT系の仕事に転職しました。32歳の時に、一念発起して海外留学に挑戦し、海外留学経験後、海外展開を行うデジタルマーケティング会社に就職をしました。しかし、コロナでレイオフになったことをきっかけに、2020年7月に帰国し、The Digital X合同会社を創業して現在5年目になります。今も青森県弘前市在住です。
─20代前半の頃は何をしていましたか。
いい質問ですね(笑)。高校卒業後、スノーボードの専門学校に進学しました。専門学校卒業後、20歳の時に、そのままスノーボードメーカーに勤めたんです。全国のスキー場や小売店さんに対して自社の商品を営業販売したり、と比較的楽しく過ごしていましたね。一方で、自分のプライベート生活は、パチスロなどで遊び呆けていたので借金苦でした(笑)。
─借金を抱えて生きることは、心理的に大きなストレスがかかることだと思います。若い年でそのような経験をはどのように乗り越えたのですか。また、その経験からどのような教訓を得ましたか?
いや、全然乗り越えられませんでしたね(笑)。おそらく、20代でMAX借金500万円程抱えていた時期もありました。あるタイミングで、返せない状態になってしまいました。しかし、そこから「ちゃんと返さなければいけない。」と改心をして、毎月15万くらい返してましたね。
この時期を振り返ると、生きているのがあまり楽しくなかった気がします。好きなことをしているのにその仕事がめちゃめちゃブラックな感じで、要は体育会系だったんです。スキーとかスノーボードに関して。なので『理不尽』ってこういうことか、っていうのはすごく社会に出てわかりました。好きな仕事にしたはずなのにどんどんその仕事が嫌いになっていくみたいな感じになりまして、最初その会社を辞めてから、IT系の会社に転職しました。
上京前と現在の、地元への思い
─高校生のときは、地元弘前市のことはどう思っていましたか。
正直言ってめっちゃクソみたいだと思っていましたね(笑)。17、18歳のときくらいからすると、遊ぶところも全然ないし、娯楽もないし、エンタメがないし、あとは洋服とかも買える場所が少ないし、なんて理由で、なんだかすごくつまらないな、と思っていましたね。
やっぱり歳が変わったか自分の趣味嗜好が変わったかわからないですけど、今は全然変わってて、住みやすいしコンパクトなところだし、どこか落ち着いていていいな、と感じます。プラス思考の価値観が増えて住みやすくなる感覚があるのは、一通り経験したからじゃないかと思っています。
「限界を超える」――『The Digital X』起業と今後の展望
─それでは、インターンプロジェクトに関しての質問をさせてください!年末のお忙しい中、本プロジェクトに参加したのか、きっかけと理由をお願いします。
え、淨法寺さん(注:本プロジェクト主催 材株式会社 代表取締役)に「やってよー」と言われたからですかね(笑)!それはさておき、弊社の事業内容は、青森の中はもちろん、東北の中でも希少なものです。日本の中でも珍しい事業内容だと思います。「The Digtal Xで働きたい!」という人がいれば、「誰でも受け入れる」という体制です。ですから、今回が特別!というわけではなくて、「いつでも一緒に働きましょう!ウェルカムです!」というカルチャーです。
─The Digital Xも、奈良岡さんも、少し硬派な、敷居が高そうなイメージがあったので意外です。(笑)それでは、創業のきっかけを教えてください。
元々、タイにあるデジタルマーケティング事業を行う企業のカントリーマネージャーを担当していました。しかし、2020年4月頃、丁度新型コロナウイルスの影響で、ロックダウンが始まりました。タイでの会社のビジネスの新規立ち上げ責任者というポジションだったのでカントリーマネージャーという役割をもらっていたんです。ただそういうB to Bの営業がそもそもできないような状況になってしまい、ヘッドクォーターからクビを言い渡されてレイオフになりました。どうしようかな、と思ったタイミングで丁度ビザもなくなって帰国せざるを得なくなった、というだけの消極的起業です。もう帰るところもないし、とりあえず支援金とか補助金もらえそうだからやってみるか、と思い起業しました。
―ではクライアントゼロの状態から始めたということになりますが、初めてのクライアントは誰だったのでしょうか。
いい質問ですね!今だから言えるのですが、そのクビになった会社の競合でした。なぜなら需要があることは知っていましたからね。同じようなノウハウを持って、すぐにコンサルで活躍できるのはそういう会社だったので、話をして、好感触だったので契約に至りました。でもその契約は3か月で終わってしまいました。それは今でもすごく身になっているんですけれども、どこか勘違いしていたところがあったんですよね。今後は一生懸命やろう、と思えるきっかけにもなりました。
―The Digital Xが存在・存続する意味を教えてください。
今年、というかつい最近ですね。会社としてのビジョン・ミッション・パーパスを設定しました。我々のビジョンは『breaking boundaries』といいます。日本語で言うと世界の境界をなくす、という意味なんですけれども、この英語の中には『限界を超える』という意味も含まれています。我々がやっている事業は海外、グローバル向けのデジタルマーケティングのコンサルティングがメインなので、そことリンクをしていると思います。それではなぜ我々が存在してるか、というパーパスのところなんですけれども、『To lead our clients, business grows globally with digital』、つまりクライアントのグローバルな成長をデジタルでリードする、というのを我々のパーパスにしています。だから我々が存在している、という意味づけにもなっています。
―5年後のビジョンをお願いします。
5年後はですね、世界約40か国にその国や地域出身の仲間がいるような世界を作りたいです。なぜなら10年後には世界約200か国に、すなわち全世界に我々の、The Digital Xの仲間がいる、という状態を作りたいからです。ですので、逆算して5年後にはそれくらいの規模にしなければならないと強く感じています。
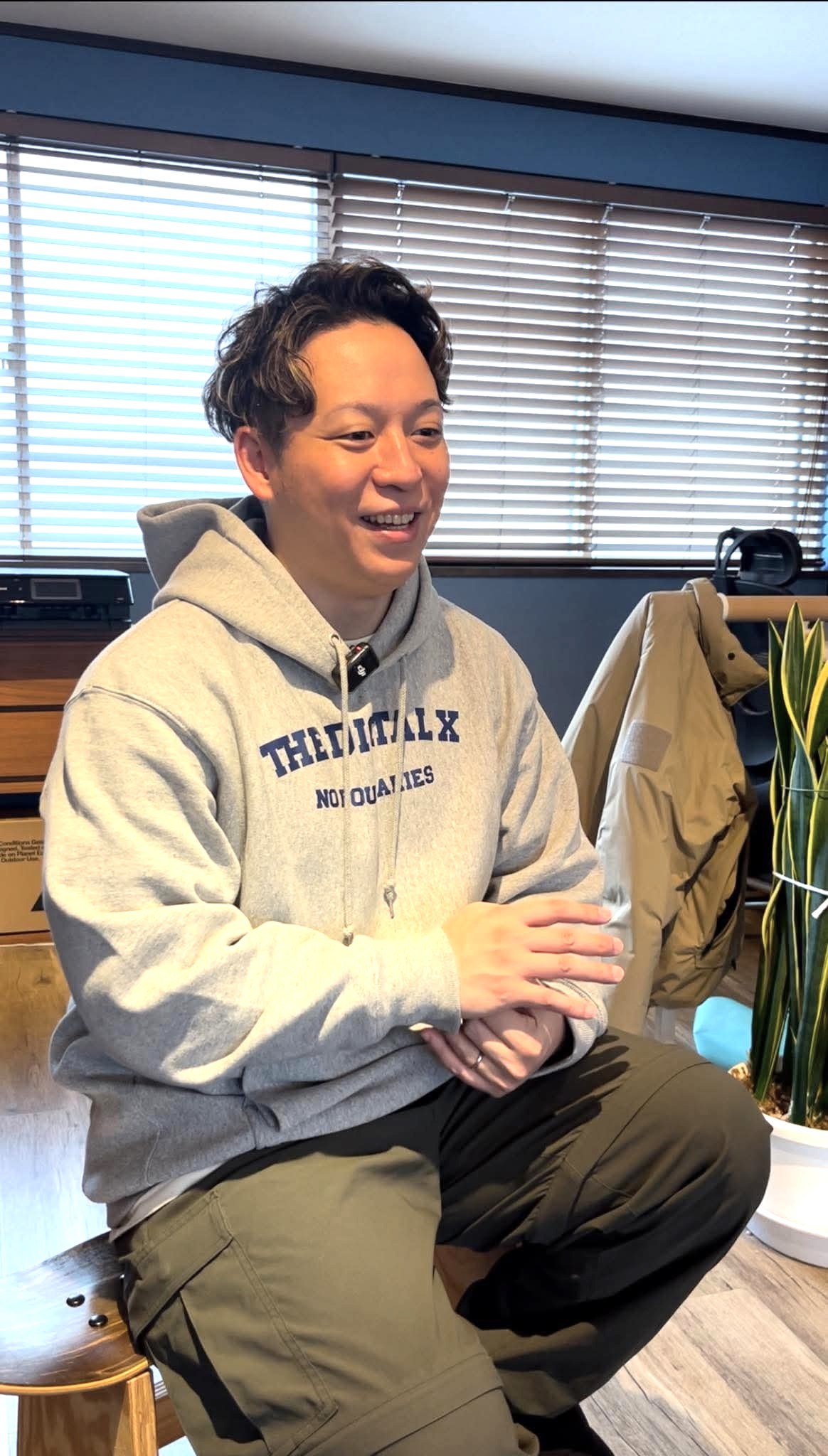
学生へのメッセージ
―今回参加したインターン生や彼らと同世代の人々にメッセージをお願いします。
5年前と現在を比較すると、5年前だとフィジカル的に職場が近くになければダメだとか、引っ越ししなければダメだ、といった規制がありました。しかし、「でも仕事ないよね、帰ってもやりたくない仕事が多いし」という人ばかりでした。けれども、今はフルリモート等を活用すれば東京からでも今すぐ働けますよね。だから働き方は多様だと思います。例えば引っ越したかったら引っ越して来ればいいんです、特にうちに関しては。ただ様々なところで言っているように、「どこにピンを刺して、どこを向いて仕事をするか」が大事だと我々は考えています。例えば我々は青森にピンを置いていますが、向いているところは世界です。そういった形態で場所にとらわれず働けるようになったらいいな、と思いますね。
インタビュアープロフィール
古井茉香
八戸聖ウルスラ学院高等学校出身。早稲田大学社会科学部2年在籍。頑張る意味や生きる意味を見失う学生と多く出会い、自身もインターンとしてかかわる傍ら、地域企業に貢献しながら自分の将来の暮らしを考える機会を作りたいと思い本企画の運営を行う。
記事執筆者プロフィール
川村実愛
青森高等学校出身。早稲田大学商学部2年。今回は長期休み期間中やることがないため、古井の紹介により参加を決意。




